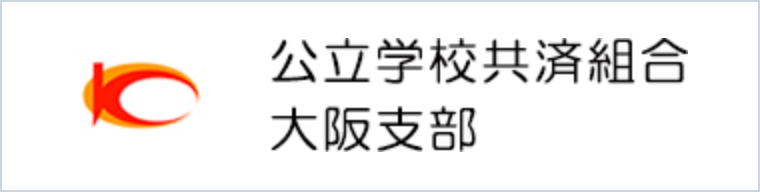相談の事例
ご相談内容は、仕事のこと、心身の健康のこと、家庭のこと、なんでも結構です。
「こんなふうに頑張ったので聞いて欲しい」「愚痴を言いたい」「最近の自分について振り返りたい」というように、とにかく話を聞いて!というご利用も大歓迎です。
管理職の方は、職員対応や職場環境(ラインケア)に関するご相談も可能です。
下記に、ご相談の事例をまとめましたのでご参照ください。
ラインケア
- 対象者
- 管理職対象 職場の状況や職員の方についてのご相談
事例① 心身に不調をきたしている職員への対応について(小学校 校長)
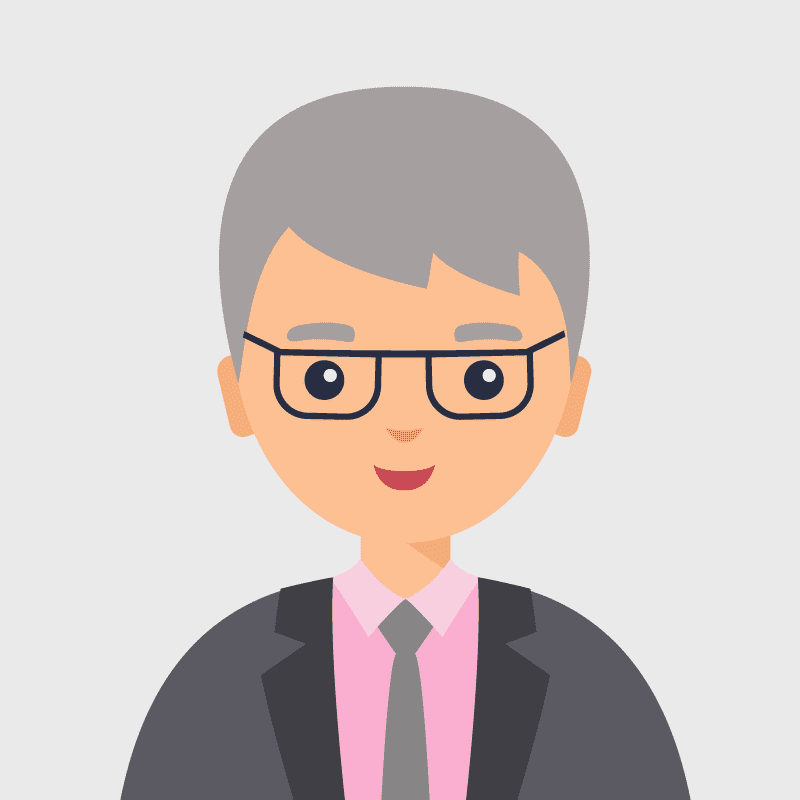
職場に心身の状態が気がかりな職員がいて、どんな支援ができるとよいかを聞きたいと思いました。どう声を掛けるのがよいか、どんなことを伝えるとよいかなど、具体的な関わり方について相談しました。
スタッフの対応
当該職員の方の個々の事情を聞きながら、メンタル面の不調に関する一般的な理解の仕方について説明し、具体的な声のかけ方などについて考えました。今後必要な時に役立てていただくために、受診を促すタイミングや伝え方などについてもお話しました。
相談者の感想
心身に不調をきたしている職員に対する具体的なサポートの仕方について知ることができました。当該職員に応じた細かい留意点についても確認することができてよかったです。
事例② 休業中の職員について(中学校 校長)
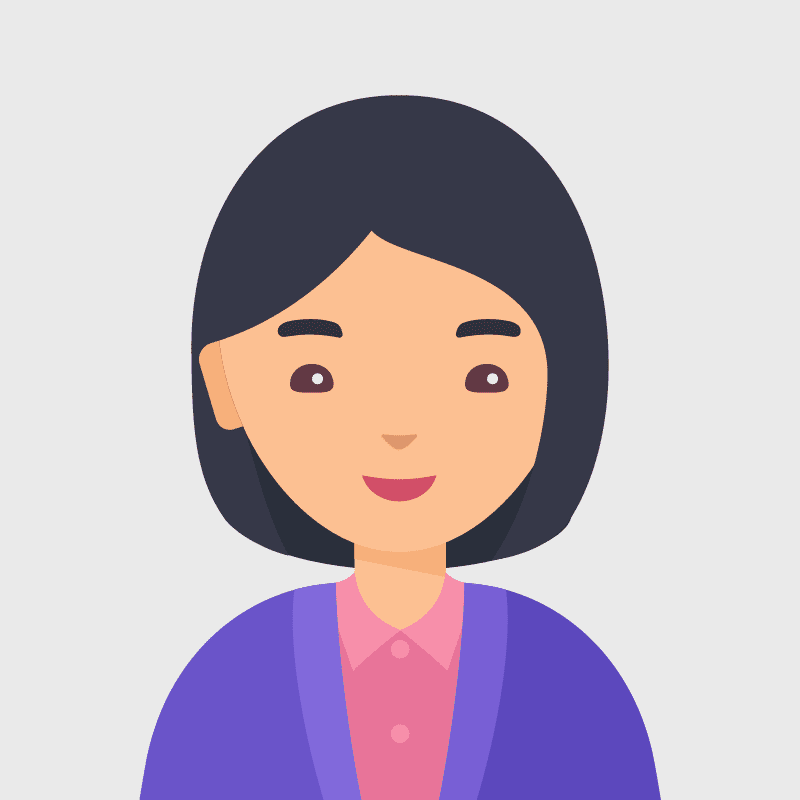
職員が(メンタル面の不調で)休業に入りました。休業中、管理職としてどのように関わっていけばよいかを聞きたいと思いました。また、当該職員が休業中、他の職員をどうサポートしていくのがよいかについても相談しました。
スタッフの対応
当該職員の方の状況を聞き、休業に入る時に伝えておけるとよいことや休業中の連絡方法、その際の配慮事項などについてお伝えしました。職場の状況もお聞きし、他の職員の方へのサポートについても一緒に考えました。
相談者の感想
考えていた対応で概ねよかったことがわかり安心しました。休業中の状況に応じて、また相談していきたいと思いました。
事例③ 対応の難しい職員との関わり方について(高等学校 教頭)
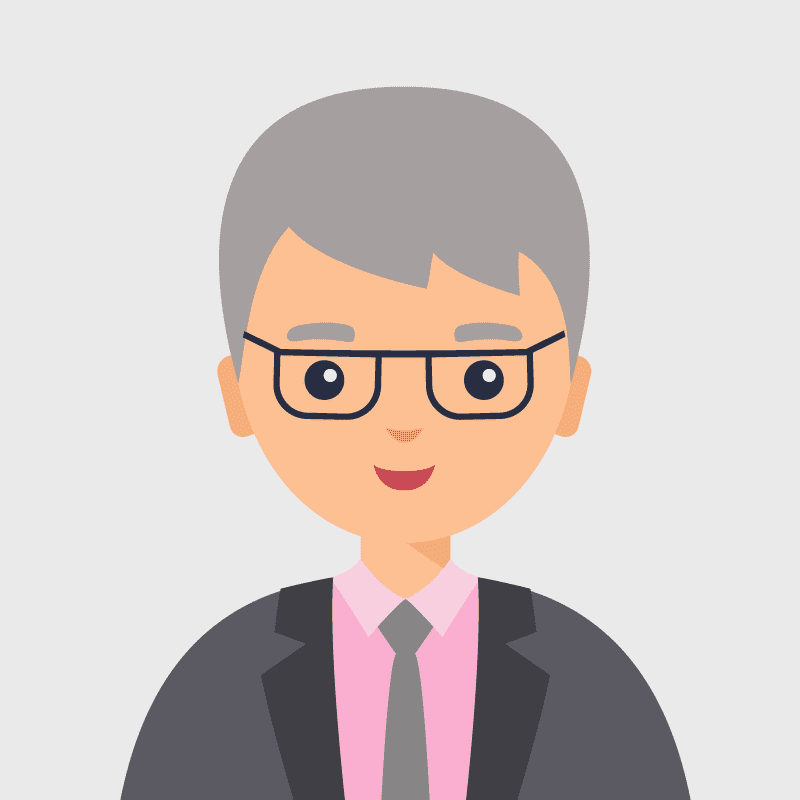
計画的に仕事をしていくことが苦手で、状況に合わせた臨機応変な対応が難しい職員がいます。期限になっても書類が整わないことが頻繁で、予定変更があるとすぐに対応できなくなります。周りの職員とのコミュニケーションが上手くとれず、関係が難しくなってきていることも心配です。発達特性のグレーゾーンなのではないかと考えていますが、どう理解して、どうサポートするのが職場にとってよいのか相談したいと思いました。
スタッフの対応
相談者がねばり強く対応されていることをねぎらいました。また、状況をうかがい、どんなことが上手くいっていないのか、どうしてそうなるのかについて一緒に考えました。当該職員とどう話し合うか、どうすれば改善するかについての具体的な方法も話し合いました。他の職員の当該職員に対するネガティブな気持ちが大きくなっていかないようにするために、周囲の職員の思いを聞いて、ねぎらいの言葉をかけることも大事と提案しました。
相談者の感想
具体的な対応方法を考えることができたので、一度やってみたいと思いました。当該職員や周囲の職員らの思いもしっかり聞いてみることにしました。その後の経過を報告しながら、また相談を続けたいと思いました。
セルフケア
- 対象者
- 全教職員・ご家族対象 ご本人またはご家族の不調や悩みについてのご相談
事例① 心身の不調について(小学校 教員)
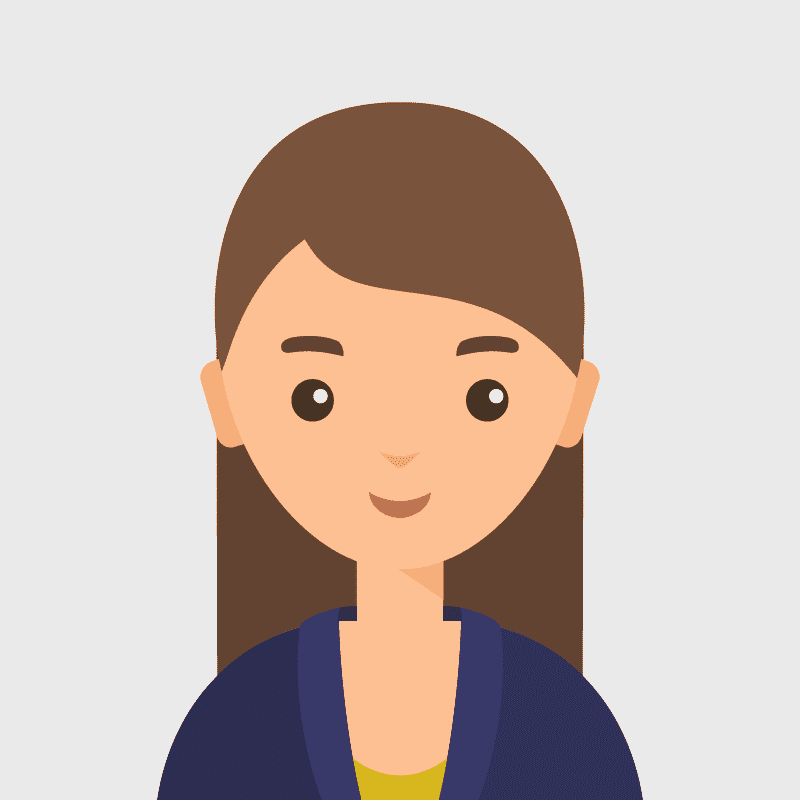
最近、朝に吐き気や腹痛がして出勤時間が遅くなってきています。先日は、遅刻の連絡をしたのですが、その後出勤することができませんでした。夜はなかなか寝つけず、夜中に何度も目が覚めます。かかりつけ医に相談すると、腹痛や不眠はストレスが要因ではないかと言われ、精神科を受診することを勧められました。精神科を受診には抵抗があり、薬を飲むのも心配でためらっています。
スタッフの対応
症状や状況について詳しくうかがい、体調が悪く、不眠や出勤しづらい状況が続いていることを、どう理解し、どう対処していくのがよいのかについてお話しました。また、受診を考える目安についてもお伝えしました。服薬について、どんな不安があるのかをお聞きし、それを医師に相談するようにお勧めしました。
相談者の感想
自分が我慢して頑張りすぎていたことに気づき、できるだけ休養を取るようにしようと思いました。思い切って受診し、服薬について不安に思うことを具体的に医師に伝えて相談してみようと 思いました。
事例② 休業や復職について(支援学校 教員)
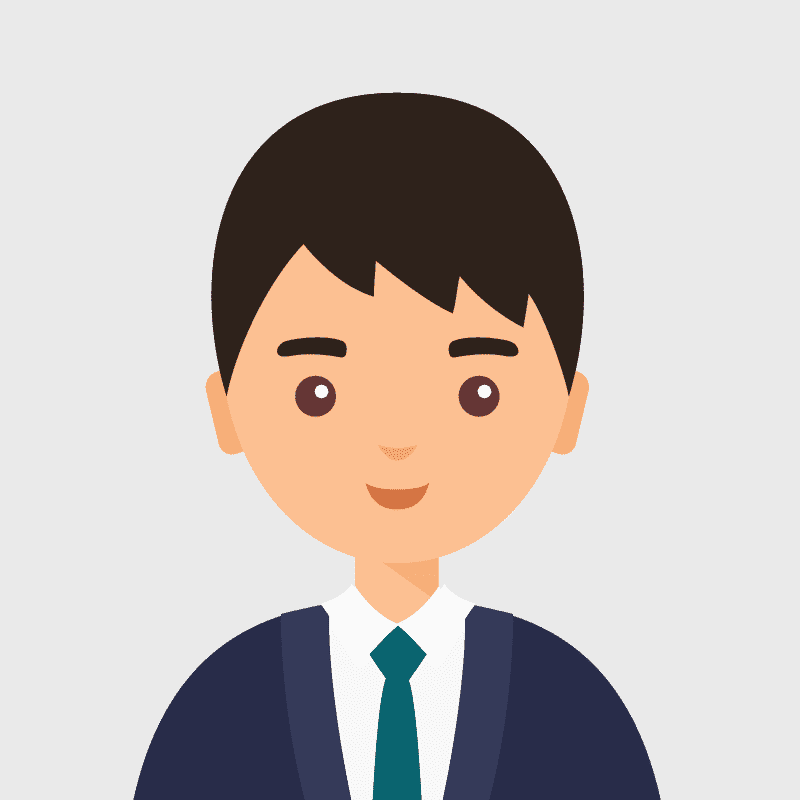
最近、メンタル面の不調で休業に入りました。担当していた生徒のことを考えると申し訳ない気持ちになり、早く復職しないといけないと思って焦っています。これからどのように過ごしていけばよいかわからなくて不安な気持ちで一杯です。休業中の過ごし方やこころの持ち方、復職を考える目安などについても相談したいと思いました。
スタッフの対応
いま感じておられるいろいろな気持ちをうかがい、病状の回復段階に応じた過ごし方、「いまできること」「いま考えられること」を一緒に確認しました。療養の初期の不安な気持ちに寄り添いながら、いまは復職を考えるより、まずは症状を改善することに専念し、休養することをお勧めしました。
相談者の感想
復帰を焦りすぎていたことに気づくことができました。自責的な気持ちが強くある一方で、休 業に至る過程ではいろいろと理不尽な思いをしてきたことを振り返ることもできました。話をしていくうちに、少しは頑張ってきた自分をねぎらいたい気持ちにもなりました。療養の中期、復職前、復職後など、それぞれの時期に過ごし方に迷ったら相談しようと思いました。遠方なので、 オンライン相談も利用しようかと考えています。
事例③ 働き方について(中学校 教員)
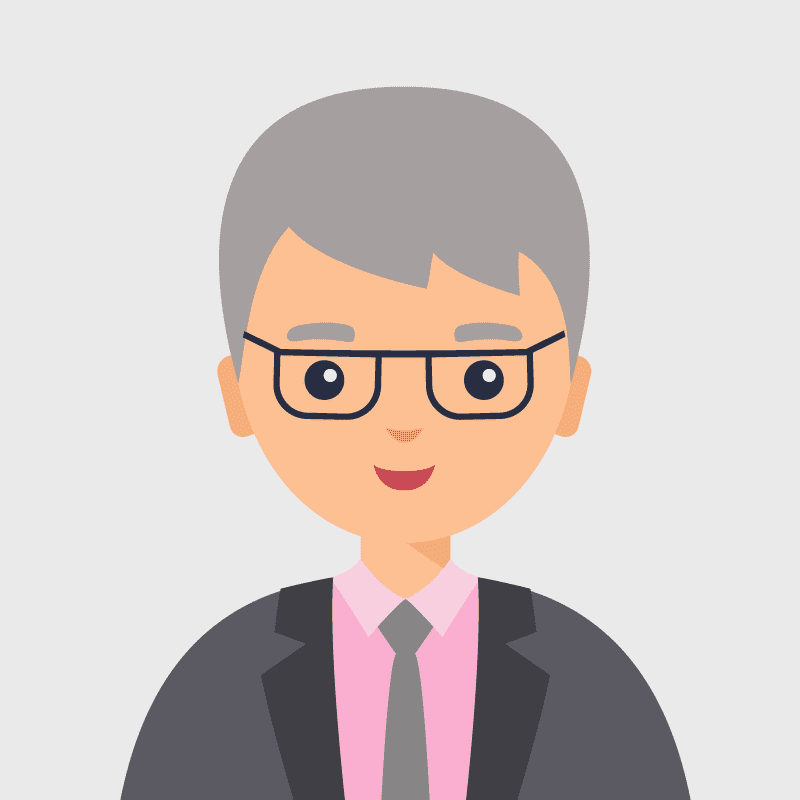
土日もクラブ活動や授業準備などで出勤することが多く、休日がほとんどないのが当たり前の生活です。ずっとこの働き方をするのかと思うと、仕事を続けていけるのか心配です。今後、家庭の状況により時短勤務や介護休暇などを取りながら働くことも考えていますが、それがいいのか迷っています。
スタッフの対応
人生におけるワークライフバランスや自分らしい人生の過ごし方などについて話し合いました。負担感や不安がありながら頑張って働いているのには、どんな思いがあるのかを一緒に考えました。また、時短や休暇の制度を利用することをためらう気持ちについても話し合いました。
相談者の感想
一人ではなかなかゆっくり考える時間を持てないので、思い切って相談に来てよかったです。少し立ち止まって自分のことを考えてみる機会になりました。制度の利用についても、考えが漠然としていましたが、一緒に考えることで整理できました。自分の状態や家庭の状況などを後回しにせずに考えていこうと思いました。
事例④ 子ども、保護者対応について(幼稚園 教員)
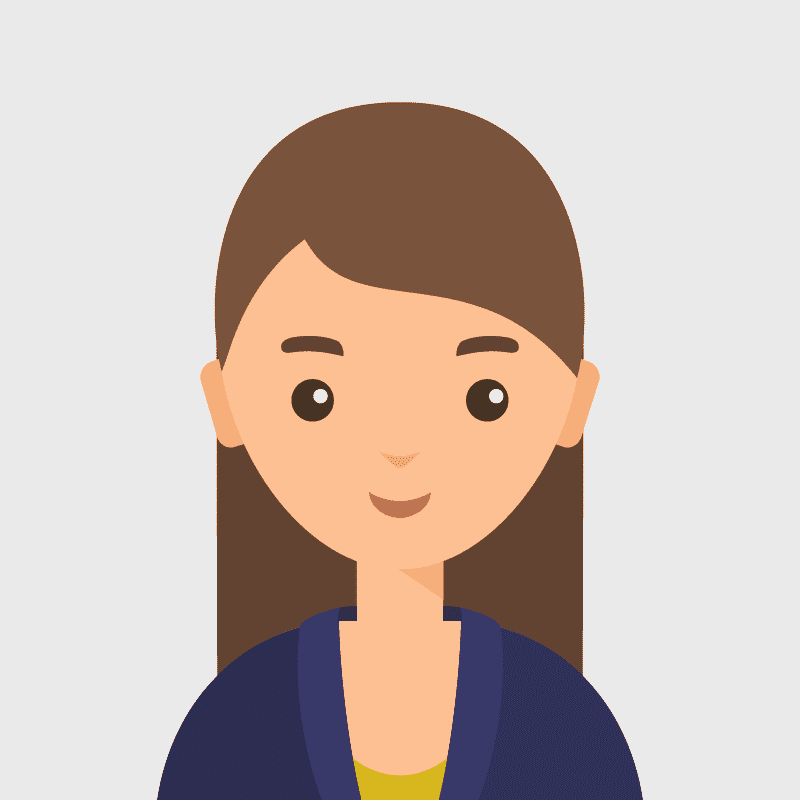
クラスが落ち着かず、思うように保育ができないで、ついイライラしてしまい、園児を叱ってばかりになります。また、保護者に園児の気がかりな様子を伝えると、「家では問題ない。全く心配していない」と言われてしまいました。その後関係がギクシャクするようになり、保護者との接し方について悩んでいます。
スタッフの対応
不安な気持ちや自信のなさなど、ありのままの気持ちをおうかがいしました。難しい状況の中で頑張っておられて、できていることも多いことをお伝えしました。保護者の気持ちや家庭の事情を一緒に想像してみたりもして、具体的な対応方法について話し合いました。
相談者の感想
できていないことばかりに目が向いていましたが、できていることも多いと言ってもらって、ほっとしました。自分の気持ちを自由に話せて気持ちが落ち着き、クラスの状況を客観的に振り返ることができました。保護者への伝え方も工夫してみることにします。
事例⑤ 同僚との関係について(小学校 事務職員)
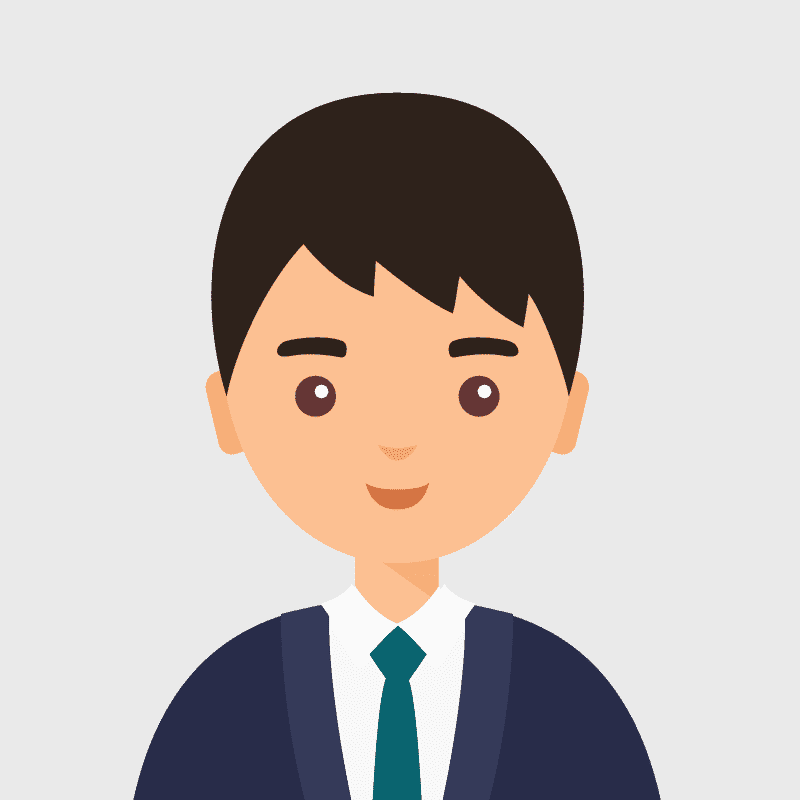
転勤後の職場が大規模校で、複数配置の職員との関係でしんどくなっています。同僚の仕事の進め方について、自分の考えを伝えてみましたが、同僚は自分の考えがあって強く拒否されました。それ以来、話がしにくくなっています。多くの仕事をこなさないといけなくて大変な中、わからないことがあっても聞けないし、教員の同僚らは皆忙しそうで、孤独感が大きいです。
スタッフの対応
新しい職場に早く慣れようとして、とても頑張っておられるとお伝えしました。仕事の分担や、適度に距離をとることなど、お互いのストレスが少なくなる方法を話し合いました。また、管理職に相談してみることも提案しました。
相談者の感想
自分が思っている以上に頑張りすぎていることに気づきました。同僚には同僚の考えがあり、それを変えようとすることは難しいと思いました。孤独感を解消できるように、他に話ができそうな職員がいないかなど、管理職にいろいろ相談してみようと思います。
事例⑥ 家族やプライベートの状況について
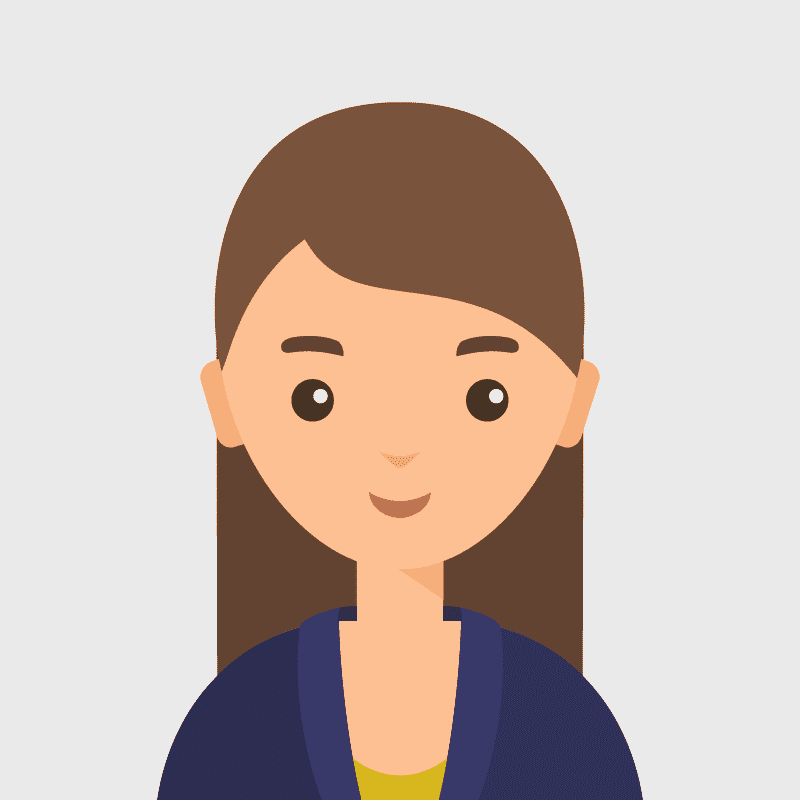
息子(娘)が学校に行かず/卒業後定職につかず、昼夜逆転の生活になっています。家で寝ているか、ゲームをしているかで、本人も焦りがあるのか、時にイライラして荒れることもあります。どう接していったらいいか相談したいと思いました。
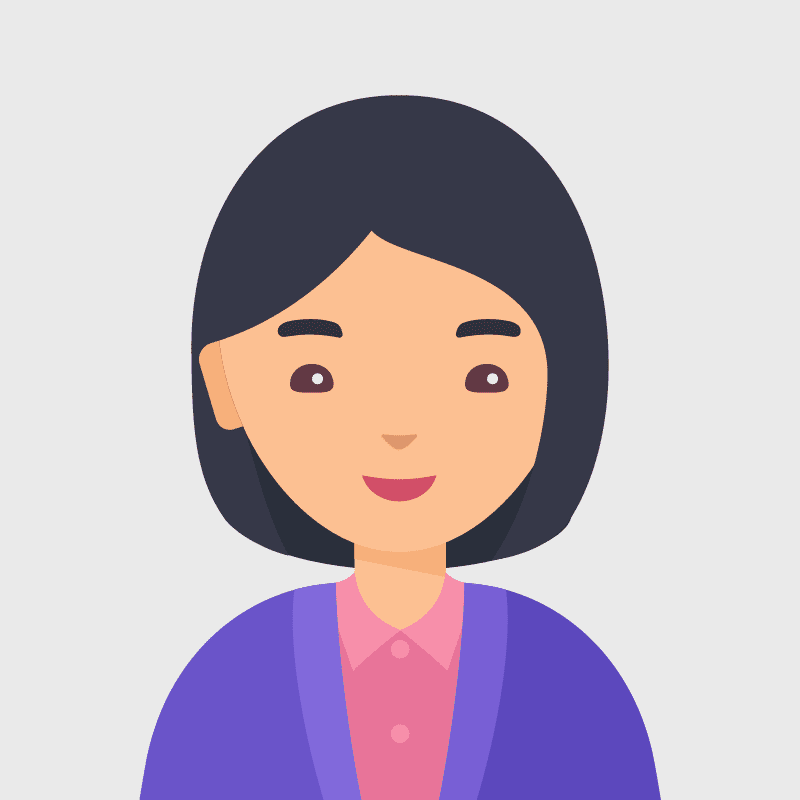
最近、夫が些細なことで怒るようになりました。仕事が忙しく、疲れているとは思うのですが、こちらも仕事で疲れていて気持ちに余裕がないので上手く対応できません。離婚を考えたりもしますが、子どものことを思うと迷ってしまいます。
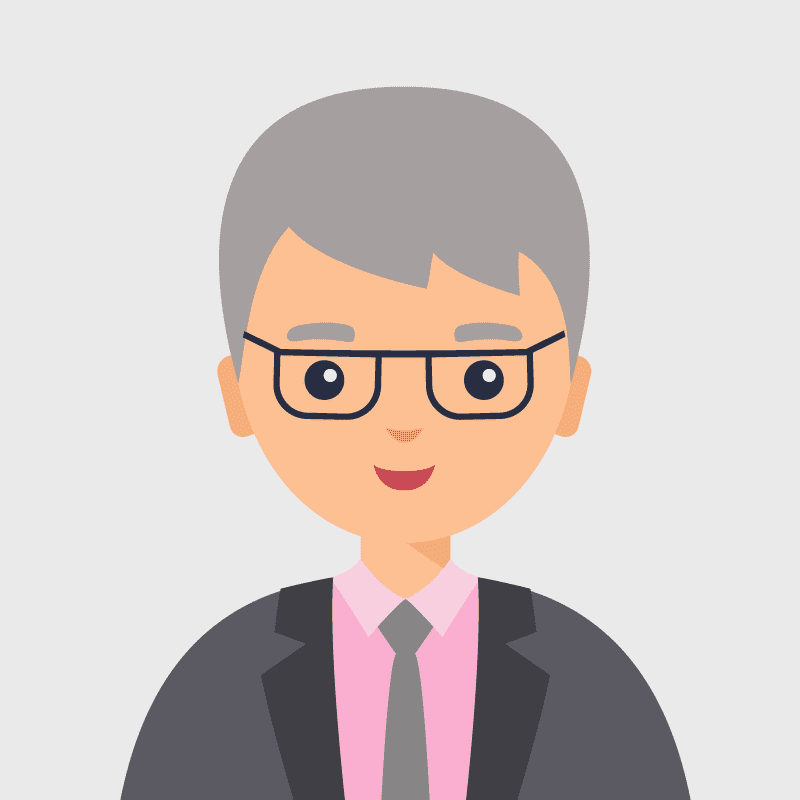
母親が認知症で対応に疲れています。訪問介護やデイサービスなどを提案してみましたが受け入れてもらえず、母親との関わりで心身ともに休まる時がありません。どうしたらいいか相談したいです。
スタッフの対応
家族のことについて、これまで一人で考え、対応してこられたことをねぎらい、具体的な関わり方や声の掛け方について一緒に考えました。誰かに話をして気持ちを整理することや、自分のための時間や場所を確保することの大切さを伝え、その方法を話し合いました。引きこもりや介護に関するより専門的な相談先の情報についてもお伝えしました。
相談者の感想
今まで誰にも言えなかったプライベートなことを話せたことで、気持ちが落ち着きました。家族のために自分が頑張らないといけないと思っていましたが、まずは自分の心身のケアが大切であると知って驚きました。自分を犠牲にして対応するのが当たり前だと思い込んでいたことに気づきました。
事例⑦ 休業中の夫の様子について(家族(被扶養者))
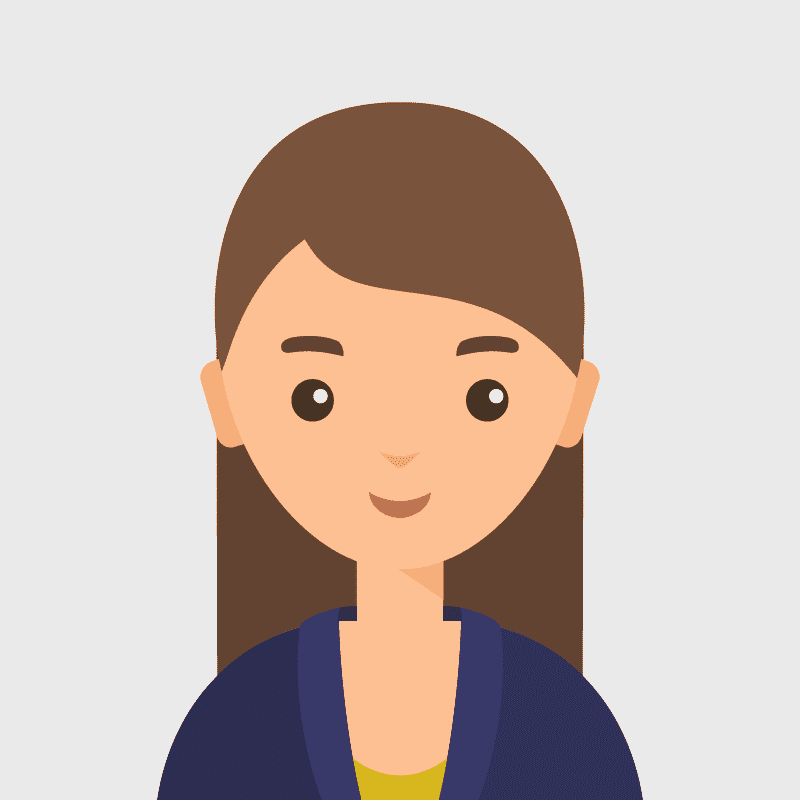
夫が休業中で、家でも元気がなく、寝ていることが多い毎日です。見ていて辛い気持ちになるし、このままでいいのか心配になっています。接し方について相談したいです。
スタッフの対応
ご家族の気持ちに共感し、気遣いながら見守っておられることをねぎらいました。療養の初期には、ずっと寝ていることも回復のために必要なことも多いと伝え、声の掛け方などについて一緒に考えました。家族が自分の時間を持ってもよいことをお伝えし、夫の病状をより理解するために受診に同伴することも提案しました。
相談者の感想
夫の様子について、いまはこれでいいのだとわかって安心しました。夫に厳しい目を向けがちな自分を責めていましたが、家族のストレスもわかってもらえたのでよかったです。お互いに無理をしないようにしようと思いました。次回の受診日には、夫の承諾を得て診察に同伴し、サポートの方法を相談してみます。
若手教員の相談事例
事例 2年目の悩み(小学校 教員)
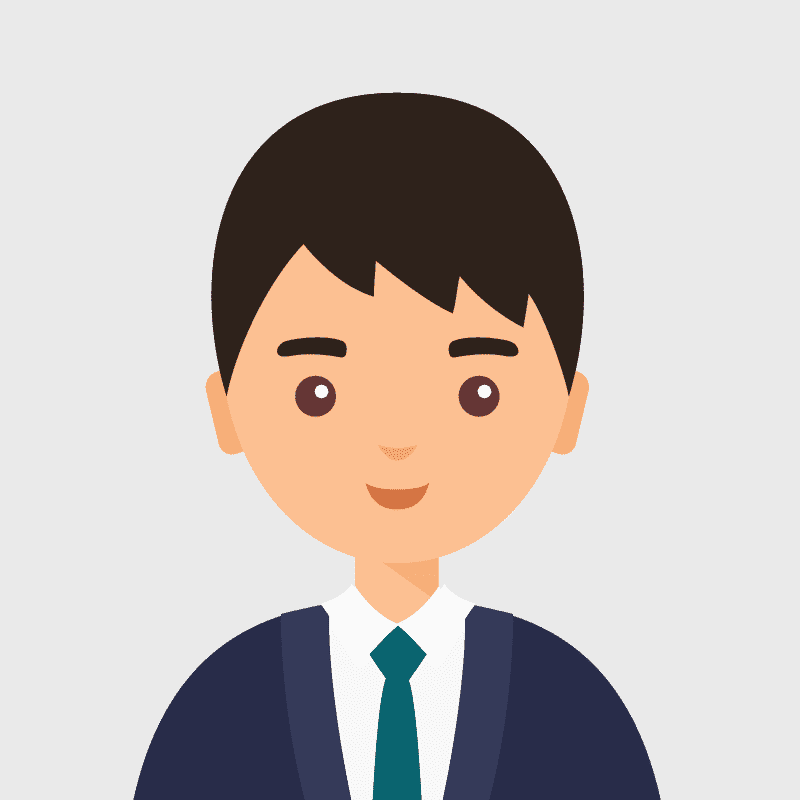
1年目は、よく分からないことだらけで不安でいっぱいでしたが、先輩の先生方に助けてもらい、なんとか終えることができました。
2年目で高学年の担任になりましたが、クラスが落ち着かず、生徒との関わりに自信が持てなくなっています。夜遅くまで授業の準備をして、その後すぐに寝つけなかったりして、疲れが溜まってきています。
1年目の後輩がしっかりやっているのに情けなく、管理職や保護者からどう見られているのかも気になって、食事がのどを通らなくなってきました。
スタッフの対応
2年目になって、1年目とはまた違った悩みが出てきたことについて、その気持ちや思いを語ってもらいました。一人ひとりの生徒に丁寧に関わり、いまできることを一生懸命やっておられることを確認しました。焦りや不安が生じると、人の言葉や態度を悪く解釈してしまいがちになることもお伝えし、一人で抱えて頑張るのではなく、周囲に相談したり助けを求めたりしながら働いていくことの大切さについて話し合いました。
相談者の感想
こんなことで悩んでいるのは自分だけではないかと、ずっと不安でした。このような相談は、もっと大変な思いをしている人が行くところと思い込んでいました。「もう2年目なんだから」と思って気負い過ぎていたことに気づけて、この1年の自分なりの目標について考え直すことができました。どんな悩みごとでも相談してよいことがわかり、またこれからも利用していこうと思いました。